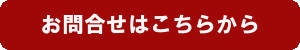アメリカで雇用するために絶対に知っておきたい【アメリカ就労ビザ】重要ポイント!


アメリカで雇用するために絶対に知っておきたい【アメリカ就労ビザ】重要ポイント!
近年、グローバル化に伴って海外に進出する企業が増加しています。中でもアメリカは日本企業の海外進出先として常に上位にあります。ご存じのようにアメリカでは、日本人のような外国人が働くためには就労ビザが必要となります。アメリカの就労ビザの取得は容易ではなく様々な条件や複雑なプロセスがある上に、年々、取得が難化しています。そこで今回は、アメリカで雇用するために知っておいていただきたい就労ビザに関する重要ポイントをご紹介します。
アメリカのビザの種類
まず、外国人がアメリカに長期滞在するには目的に応じたビザが必要となります。アメリカのビザは「非移民ビザ」と「移民ビザ」の二つに大きく分けられます。「非移民ビザ」は就労や留学などで、滞在は限定的なもので日本に帰ることが前提となります。一方「移民ビザ」は、永住権(グリーンカード)のことで、移民としてアメリカに入国した人はアメリカに永住することを前提としています。永住権は取得すると更新手続きを行えば永久的にアメリカに居住することが許可されます。(例外あり)
アメリカのビザには下記のようなものがあります。
- A. 外交官、各国政府職員等
- B. 商用、観光による短期滞在者
- C. 通過ビザ (Transit Visa)
- D. 船舶、航空機の塔乗員
- E. 通商条約に基づいた貿易、投資
- F. 留学生
- G. 国際機関に勤める者
- H. 一時的な就業(専門職等)、訓練
- I. 外国報道関係者
- J. 交流プログラム外国人
- K. 米国市民の婚約者
- L.同系企業転勤者
- M. 職業訓練のための短期留学
- O. 科学、芸術、スポーツ等の分野で 卓越した能力を持つ者
- P. 芸術家、芸能人、スポーツ選手
- Q. 国際文化交流に参加する者
- R. 宗教関係者
アメリカで働くには就労ビザが必須!
就労ビザとは
外国人がアメリカで働く際に必須の資格です。アメリカに駐在して就労する、または現地で外国人を採用するためには就労目的に応じたビザを取得する必要があります。ビザを取得する場合、ビザの種類、有効期限などに留意することが大切です。また、ビザの取得については申請方法や審査方法などが異なり複雑です。必ず弁護士など専門家を通じて申請するようにしてください。
アメリカで就労可能なビザ
アメリカで就労可能なビザとしてよく活用されているものにはグリーンカード(永住権、移民ビザ)、L-1ビザ(同系列企業内転勤者)、H-1Bビザ(特殊技能職)E-1ビザ(条約貿易業者)/E-2ビザ(条約投資家)などの非移民ビザがあります。この他にもIビザ(報道関係者)やO-1ビザ(卓越した能力保持者)などがあります。この中で、アメリカで外国人を採用する上で最も一般的な就労ビザとして知られるH-1Bビザについて説明します。
H-1Bビザについて
H-1Bビザとは「専門技術者」として米国で一時的に就労する方を対象としたビザです。職務に一致する学士号か、それ以上の学位(もしくは同等の資格)を有することが、その職務に就くための最低必要条件となっています。
H-1Bビザの主な概要
- ビザのスポンサーとなる企業が必要
- 申請には、まずは毎年3月に行われる移民局の抽選に受からなくてはならない(当選率は2023年が約27%、2024年が約25%)
- 有効期間:3年(最長6年)
- 更新の可否:可(3年ごとで1回のみ)
- 開始時期:移民局年度により毎年10月1日開始
- 配偶者が取得できるビザ:H-4ビザ
- 配偶者のアメリカでの就労について:基本的に不可ですが特定の条件を満たせば可(詳細は弁護士に相談してください。)
H-1Bビザにあてはまる職種
具体的に専門技術者としてH-1Bビザのカテゴリーにあてはまる職種としては下記のようなものがあげられます。弁護士、医者、科学者、建築家、エンジニア、プログラマー、ITプロフェッショナル、マーケティング・アナリスト、会計士、財務アナリスト、為替ディーラー、各種マネージャー、教師、グラフィック・デザイナー、セラピストなど。
参照:
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/types-jobs-most-likely-qualify-you-h-1b-visa.html
https://www.myvisajobs.com/reports/h1b/
H-1Bビザ申請に必要なもの
まずはビザのスポンサーとなる企業などの事業主が必要です。近年、取得プロセスの複雑化、および申請費用の増加に伴い、取得は厳しくなっています。
H-1Bビザに申請するには企業などからオファーされるポジションが学士以上のレベルを要求するポジションであり、申請者がそのポジションに就くための学位あるいは職業経験を満たしている必要があります。また、スポンサーの企業(雇用主)が、米国労働省によって規定されているポジションに見合った給与を支払う必要もあります。
H-1Bビザを取得するための王道の方法としてよく言われるのは、アメリカに留学して学業を終了した後にOPTと呼ばれる研修制度を活用して企業で研修を行い、その企業からH-1Bビザのサポートを行うというものです。
OPTについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
アメリカで働きたい留学生必見! OPTとSTEM OPTについて
スリー・トゥ・ワンルールについて
4年制の大学の学歴を持っていない方も米国移民局(USCIS)のスリー・トゥ・ワン(3対1)ルールを活用することで、H-1 Bビザを取得できる可能性はあります。このルールは専門分野での3年の経験は4年制大学の1年分に相当するというもので、2年間の短大卒の場合は6年以上、高卒であれば12年以上の専門職での職務経験があれば4年生大学を卒業したのと同等に見なされます。職務経験はH-1Bを申請する際のポジションと関連したものである必要があります。
H-1Bビザを取得するにあたって日本での学位および職務経験は有効となりますが、例えば日本の大学を出ており、アメリカの専門学校などの10か月のコースでのサーティフィケート(修了書)をとった方がコース終了後のOPTからH-1Bビザを申請するのは容易ではなく、アメリカの学位に日本の大学の成績証明書をきちんとあわせて確認してみないと申請の条件を満たさないことがあります。
またH-1Bビザの申請には、職務内容が学歴と関連していること重要ポイントとなるので、雇用主が申請の際に提出する職務内容説明書に、どのようにアメリカのサーティフィケートと日本の大学の学位が職務に関連しているかを詳細に記載することが重要です。
H-1Bビザの年間発給数
H-1Bビザは、年間発給数に制限のあるビザで、一般枠H-1Bビザの年間上限数は6万5,000件となっています。ただし、そのうち6,800件は貿易協定によりシンガポールとチリの国籍者に優先的に割り当てられるため、その他の国籍の人に割り当てられる数は実質5万8,200件となります。一般枠とは別に、米国の大学の修士号以上の取得者枠として別の2万件のH-1Bビザがあり、修士号以上の取得者は有利となっています。
H-1Bビザの申請の流れ
H-1Bビザの申請手続きは2020年度より、大幅に変更されました。以前までの手続きではH-1Bビザの請願は先着順で行われていましたが、年々、申請者数が莫大に増加したため、2020年よりスタートした新制度ではスポンサーとなる米国企業はまず、登録期間中にビザ申請をしたい候補者の情報をオンライン上で登録しなくてはならなくなりました。H-1Bビザの申請窓口は毎年3月に開設され、申請期間は例年2-3週間です。登録が通常、H-1Bビザの上限である8万5,000件を大幅に超えるため3月末頃にUSCISにより抽選が行われます。そしてこの抽選で選ばれた申請者のみが次のステップへ進むことが可能となっています。2023年の抽選応募数はおよそ78万件で、抽選当選率は約27%。2024年の抽選当選率は約25%であったとされています。米国修士・博士号保持者は、まず通常枠の抽選を受けた後に、上級学位枠の抽選を受けることが可能なため、選考率が高くなり有利です。
参照:https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models/h-1b-electronic-registration-process
OPT終了からH-1B就労開始までのギャップについて
留学生の方がOPT取得後に企業で研修を行い、その後、その企業がスポンサーとなってH-1Bを申請する際に注意しておきたいのは、OPTの失効日とH-1B開始日(10月1日)にギャップがある場合です。現在の 米国移民局の規定の下では、10月1日にF-1からH-1Bへのステータス変更をリクエストしている新規H-1B申請者であるF-1ビザ の学生は、申請時点でそのOPT が有効であれば、F-1ビザを維持しながらH-1B開始日までの就労が自動的に延長されます。(学校でI-20の更新は必要)。F-1ステータスの終了と H-1Bステータスの開始の間のギャップを埋めるこの規制は「キャップギャップ」と呼ばれています。OPTからH-1Bへの申請を予定されている方は、ぜひこのルールについて知っておきましょう。
H-1Bビザ申請費用について
H-1Bビザ申請費用は基本的に大きく分けると申請費用と弁護士費用となります。
*費用は2024年6月現在のものとなります。
1.申請費用
・H-1Bビザの抽選のためのオンライン申請費用(Registration Fee): 215ドル
・I-129申請費(Application Fee): 780ドル
・米国労働者トレーニング料(American Competitiveness and Workforce Improvement Act of 1998 (ACWIA) fee):1500ドル(従業員が25名以下の場合は750ドル)
・亡命プログラム料金(Asylum Fee):600ドル(従業員が25人以下の場合は、300ドル)IRC § 501(c)(3)の非営利団体(内国歳入庁から税法上の認証を得て、非営利法人として寄付行為に対する税制上の優遇措置が認められている団体)の請願者に対しては「亡命プログラム料金」は免除されます。
・詐欺防止調査料(Fraud Prevention and Detection Fee):500ドル
・国境保安法費用(Pub.L.111-230):4000ドル (従業員が50名以上で、社員の50%以上がH-1BまたはL1ビザ保持者である場合適用されます)
・特急申請料(Premium Processing Service):2805ドル(必要に応じて)
2.弁護士費用
ビザの申請プロセスは非常に複雑なので多くの方が通常、弁護士を通じて申請を行います。この場合、申請料とは別に弁護士費用が必要です。H-1Bを新規に申請する場合の弁護士費用は、およそ1500ドルから4000ドルといわれています。ただし弁護士やケースによって料金は異なりますので、正確な料金につきましては弁護士にお問い合わせください。
参照:
https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2024/02/22/a-look-at-the-high-fees-making-hiring-h-1b-visa-holders-challenging/
H-1B以外によく使用されるビザや永住権抽選について
L-1ビザ(駐在員ビザ)
L-1ビザは「駐在員」ビザとも呼ばれ、日本の会社がアメリカの関連会社に社員を派遣する場合に使われるビザです。L-1ビザビザにはマネージャーや管理者・マネージャーに発行される通算7年までのビザと、特殊技能や専門知識を持っている方に発行される通算5年までのビザの2種類があります。L-1ビザの配偶者はL-2ビザを取得し、アメリカ国内で合法的に働くことができます。
Eビザ(貿易駐在員/投資家ビザ)
Eビザは日米間の貿易や投資を活発にするのが目的の日米間の条約によるビザです。大企業から小規模のレストランやアパレルの貿易会社などでも申請可能です。投資家ビザについては必要な投資額は決められていませんが通常、専門家は10万ドル(およそ1600万円)以上の投資をアドバイスする傾向が強いと言われています。Eビザの配偶者(E-1S 、E-2S 、E-3S のステータス)もアメリカ国内での就労が可能です。
参照:
https://eb5affiliatenetwork.com/what-is-the-minimum-investment-required-for-an-e-2-visa/#:~:text=Although%20there%20is%20no%20specific,potentially%20simplifying%20the%20application%20process
グリーンカード抽選プログラムについて
アメリカには政府による公式の移民受け入れプログラムがあり、DV Diversity Programと呼ばれています。これは抽選でアメリカのグリーンカード(永住権)を取得できる制度です。例年、10月から11月初旬の間に応募の受付が行われ、当選発表は翌年5月に行われています。2023年度の応募者は9,570,291 人で当選者は54,850人となっており、当選確率は0.5%なので非常に狭き門ではありますが、アメリカで働きたい方はチャレンジする価値がある制度となっています。
【記事監修】
木村 原(Gen Kimura)
Managing Attorney
中小機構国際化支援アドバイザー
Kimura Law Office
12910 Memorial Dr Houston TX 77079
https://www.thegklaw.com/
Email : gen.kimura@thegklaw.com
Phone:832-247-6932

◆アメリカ進出のことならクイックUSAにお任せください!
アメリカ進出の困りごとをクイックUSAが解決します!
アメリカ進出において、アメリカ全土で成功をお約束する、一律のプランはございません。連邦法や各州で異なる州法に則った進出準備、そして、進出エリアの特徴を知り、特徴に合わせて企業らしさを発信することこそ第一歩となります。
例えば、カリフォルニア州であれば労働法の基準が高く、労働者からの訴訟リスクも高いため、雇用契約書面でのチェック項目を増やすようアドバイスさせていただいています。またアメリカの就労ビザの取得は複雑で弁護士による専門的な知識が必要です。
アメリカ全土に7つの拠点を持ち、それぞれのエリアで実績のある弁護士、HRコンサルタント、公認会計士などの専門家とタッグを組み企業様ごとにフルスクラッチのプランニングを提供する「クイックUSA」が、アメリカ進出成功確率を最大化します。今回はアメリカの就労ビザについて解説させていただきましたが、アメリカ進出をお考えであれば、是非クイックUSAにご相談ください。
詳細は下記の画像をクリックしてください!
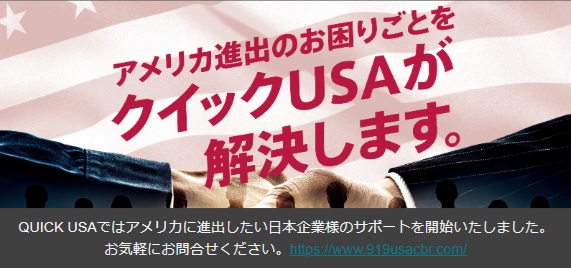
【お問合せ】
E-mail:nakagawa@919usa.com
【アメリカでのご採用をご検討中の企業様へ】
★採用でお困りなことはありませんか?
クイックUSAでは、アメリカでのご採用のお手伝いをしています。
フルタイム、パートタイム、派遣等、御社のご採用のお手伝いをさせていただきます。
お気軽に下記までご連絡ください。
●人事・労務関連のご相談にも応じております。
クイックUSAではハンドブックの作成・見直し、ジョブディスクリプションの作成、セクハラ防止セミナーの開催など、 人事労務関連のご相談も承っております。内容、お見積りなど何でもお気軽に下記までご相談ください。
QUICK USA, Inc.
[ New York Office ] (Headquarters)
150 East 52nd Street, Suite 17001, New York, NY 10022
Phone: 212-692-0850
[ Los Angeles Office ]
970 W.190th Street, Suite 590 Torrance, CA 90502
Phone: 310-323-9190
[ Dallas Office ]
5525 Granite Parkway, Suite 640, Plano, Texas 75024
Phone: 469-626-5265
[ Chicago Office ]
10 N. Martingale Road Suite 400, Schaumburg, IL 60173 USA
Phone: 646-796-6393
[ Orange County Office ]
2211 Michelson Dr, Suite 900, Irvine, CA 92612
[ Atlanta Office ]
303 Perimeter Center N Suite. 300, Atlanta, GA 30346 USA
Phone: 404-706-5266
[Detroit Office]
39555 Orchard Hill Place Crystal Glen, # 600, Novi, MI 48375
Phone: 847-791-2504
【アメリカでのご転職・就職をお考えの方へ】
★アメリカでのお仕事探し、就職・転職はクイックUSAにお任せください。
弊社のサービスにご登録がお済みでない方は、まずは英文履歴書のご登録をお願いいたします。
www.919usa.comより、オンライン登録をしていただくか、
quick@919usa.comまでE-mailにて英文履歴書を添付ファイルにてお送りください。
折り返しご連絡させていただきます。
※クイックUSAではニューヨークとロサンゼルスを拠点に全米で、留学生や社会人の求職者に対してアメリカでの就職・転職のお手伝いをしています。ご紹介しているお仕事は、金融、会計、IT、輸出入、人事、営業など多岐に渡ります。
雇用形態はお仕事をお探しの方のライフスタイルに合わせて、 フルタイムのお仕事とテンポラリーのポジションをご紹介。 クイックUSAでは経験豊富なリクルーターが、求職者の皆様一人ひとりのご希望などを伺いアメリカでのキャリアプランを一緒に考えさせていただいています。 アメリカでお仕事をお探しであれば、アメリカ求人多数のクイックUSAに是非ご登録ください!(無料)
★★クイックUSAにレジュメのご登録がまだの方は、今すぐご登録ください!★★

クイックUSAでは、ご登録者の方に対して無料のキャリアカウンセリングを実施しています。
★★Emailにてレジュメを送るだけで登録完了のエクスプレス登録もご利用いただけます!★★
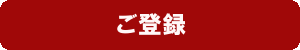
アメリカで現在お仕事をされている方、OPTや学生の方など、現在アメリカに住んでいらっしゃる方へ
アメリカでのご転職・就職で何かご質問がございましたら下記よりご連絡ください。